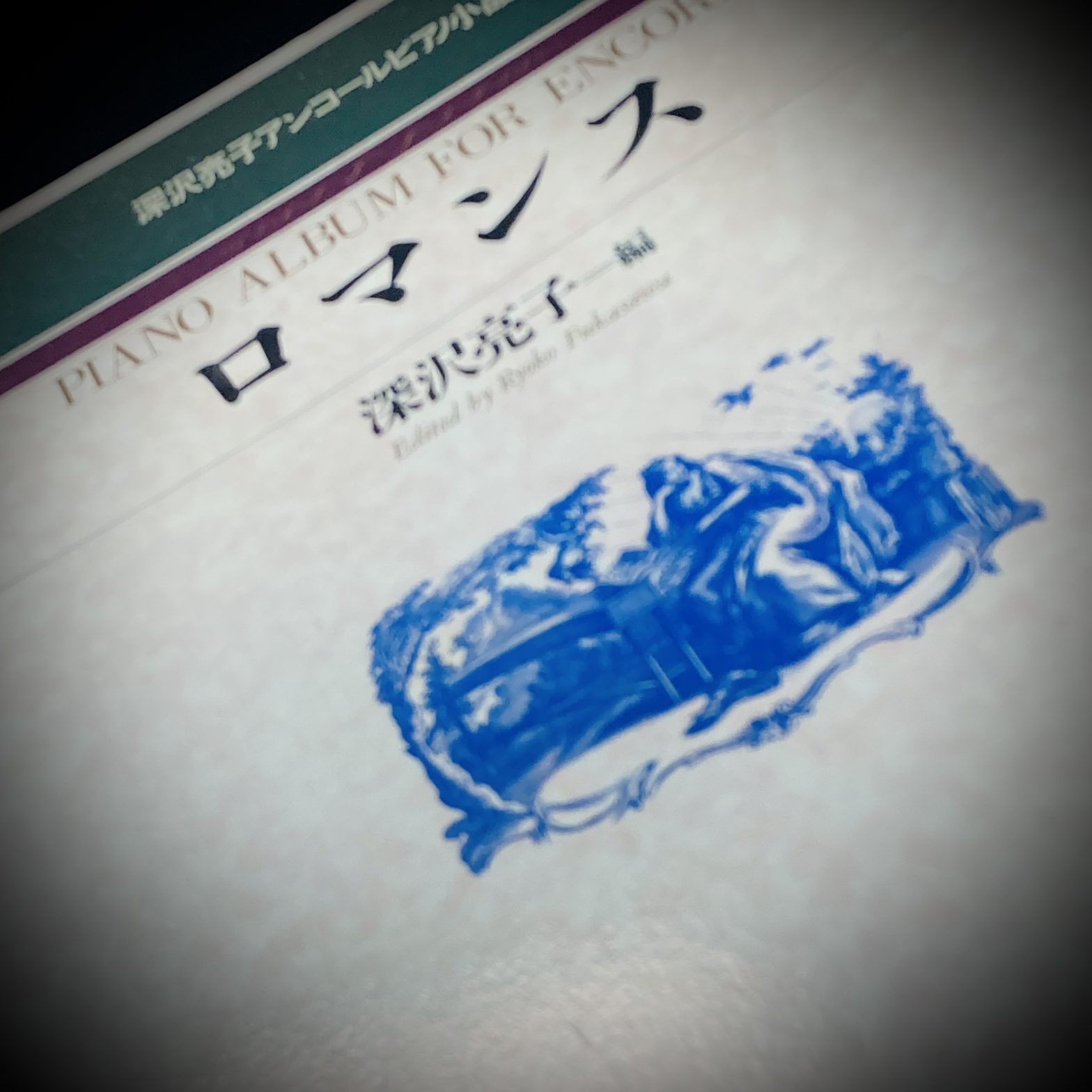by mezzopiano
「深沢亮子」
この文字を見るやいなや楽譜棚に手が伸びた。
ピアニストにそれほど明るくない私ですら知っているピアニスト・深沢亮子。
小学生のとき、たった1度だけコンクールで入賞したことがある。チャイコフスキーの《四季》から〈6月 舟歌〉を弾いた。コンクールは10月か11月なのに、なんで6月なの、と先生に言われた。
入賞に無縁な生活を送りすぎた私は、審査結果発表の会ではいつも「金賞またアイツや。」といつもの彼を確かめるだけだった……ので、自分の名前が呼ばれた時は心底驚いた。……金賞はいつものアイツだったけれど。
先生は各審査員からの講評をペラペラと見ながらこう言った。「入賞はたまたまやからね。ほら、審査員のコメントも大して良くない。あ、1人だけ、こんなに褒めてるから入賞出来たみたいなもんやから。調子乗ったらだめ。また頑張りなさい。」
文字を打っているだけでも涙が出そうだ。こんなの叱咤激励じゃない、「叱」だけではないか。先生は厳しい。大人になってみて思えば、負けず嫌いなのにサボりやすい私の性格を熟知した、よく出来た激励なのだが、コンクールに「出させられていた」小学生の私は、それはもう腹が立った。「頑張ったのに!少しくらい褒めてくれたっていいのに!いつもいつも叱ってばっかで。もうコンクールなんか出るかボケ。
翌年以降、大人になるまでコンクールとは無縁のピアノ生活を送ることとなる。
しかし調子の良い私は聞き逃すはずがない。「あ、1人だけ、こんなに褒めてるから入賞出来たんやから。」の言葉。どなたです?私を褒めてくださったのは。1枚ずつ確認する。本当に1枚だけ、とても褒めてくださっている講評が……そこに書いてあるのは「深沢亮子」の4文字だった。
何と書いてあったかはもう覚えてない。でもあの日の私は、初めて自分のピアノを評価してくれた、どこの誰かも知らない「深沢亮子」を拠り所にしたのだった。思い出補正もあるのかもしれない……そこまでの褒め言葉が書いてあったとは思いにくいが……自分の演奏に温かい眼差しが向けられることがこんなに嬉しいとは思わなかった。
それ以来「深沢亮子」という文字を見かけるたび、どこか懐かしい気持ちがぽ、と浮かんでくるのだった。
そして先日、深沢亮子が編集したアンコールピース集を偶然見つけてしまった。
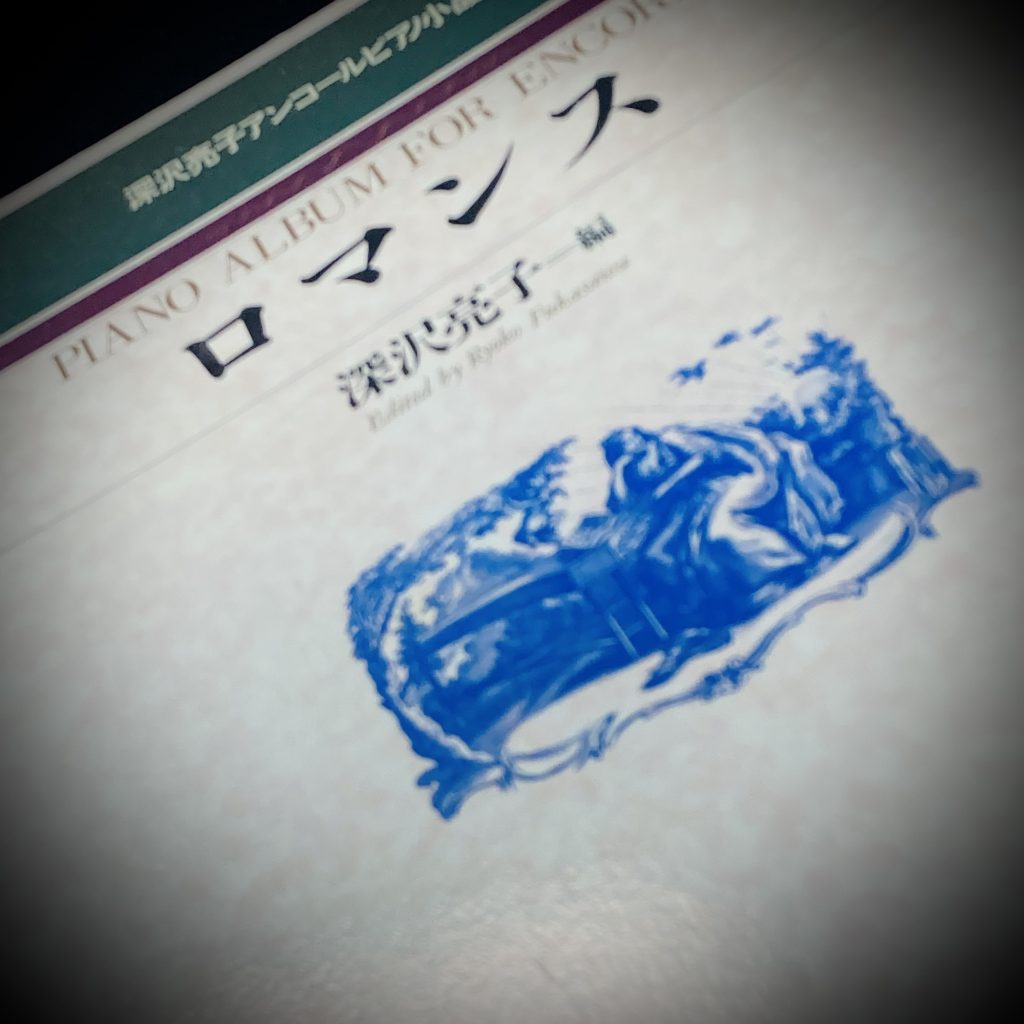
私はブックオフの楽譜コーナーを定期的に徘徊するのが趣味である。「珍しいけど佳曲」に出会う喜びは大人になってもずっと音楽を続けている理由の一つかもしれない。邦人作曲家のピアノ曲は私が大事にしていきたいジャンルで、邦人作品が入っているとなると、なおさら一体どんなものなのか確かめたくなってしまう。
この小品集はすごい。モーツァルト、シューベルト、ベートーヴェン、リストという特A級に有名な作曲家の珍しい小品、そしてC.ポルムベスク、H.ヴォルフ、日下部憲夫、原田稔、となかなか他の曲集では見ることのできないメンバーが並んでいる。買うしかない。
ぱらぱらと弾いてみたところでは、特にシューベルトと原田稔の作品が気になった。
シューベルトは言わずもがな、美しい旋律と翳りにおいて右に出るものはいないが、収録されている《最初のワルツ集Op.9 D365》では、たった20小節ほどの小品にもその特徴が存分にあらわれている。むしろ長大なソナタよりも小品でこそ、と思えるくらいだ。きれいな小石を愛おしむように、ずっとそばで大切にしていけそうな作品だ。
原田稔の作品は《鬼遊び唄4題(作品B)》というもので、その題の通り日本の鬼遊び歌をモチーフにした作品である。日本の遊び歌や民謡をモチーフにした作品は、もとの音楽の持つ言葉のリズム、抑揚が生かされていてとても好きだ。
日本は西洋音楽においてはたいへんに後発の国であるが、日本の音楽と西洋音楽がここまで美しく融合できること、日本の音楽のにおいが立ちのぼるものを作れていること……にいつも感激する。外からの文化を受け入れて、融合し、昇華してくれた先人たちに感謝のほかない。
「アンコールピアノ小品集」と銘打っているだけあって、実際の演奏会でサッと弾かれると小さな衝撃を与えてしまいそうな佳曲が揃った1冊。
1998年発刊の曲集で、残念ながら現在新品は手に入りにくい状況である。Amazonでは中古本が売っているのを確認した。(2023/9/27現在)
どこかで運良くめぐり会えた方は、ぜひお家へ連れて帰りましょう。レパートリーに新しい風を吹かせてくれること間違いなしの一冊だ。